金融庁が公的年金だけでは2,000万円不足するという報告書を取りまとめたことが話題なってから年金や資産形成に関心を寄せる人が増えています。
その中でも注目されているのが「iDeCo(イデコ)」という私的年金制度です。
加入者数は、2022年3月時点で、238万人を突破しています。
ここでは、iDeCoとはどういう制度か?分かりやすく解説しています。
日本の年金制度
iDeCoとは何かを解説する前に日本の年金制度を簡単におさらいします。
日本の年金制度には、
- 20歳以上60歳未満の日本に居住する国民の全員が加入を義務づけられている国民年金
- 会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する厚生年金
があり、これらを公的年金と言っています。
一般的には、
- 自営業は、国民年金
- 会社員は、国民年金を含む厚生年金
- 公務員は、国民年金を含む手厚い厚生年金
に加入しています。
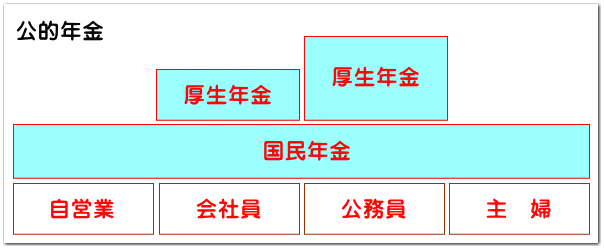
これらの公的年金に対して、企業が福利厚生の一環として独自に実施する企業年金だったり、個人が任意で加入する年金を「私的年金」と言っています。
国民年金や厚生年金などの公的年金と違い、私的年金への加入は任意です。
iDeCoとは?
iDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度です。
私的年金制度は、公的年金だけでは不足、受け取る年金をもっと充実させたい、といった場合に、下図の緑の部分を補完し、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法のひとつです。
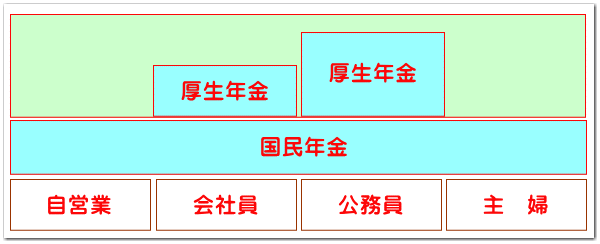
iDeCoの仕組み
私的年金制度のひい突であるiDeCoは、個人型確定拠出年金と言われており、60歳(一部65歳)未満までの間に自分で申し込んで加入することができます。
自分で、予め用意されている投資信託や預金・保険などの金融商品を選び、決まった金額を積み立てながら運用し、60歳以降に年金として受け取る制度です。
掛け金は、月々5,000円から1,000円単位で設定でき、掛金の上限は人によって異なります(掛金の上限については下で解説)。
60歳(一部65歳)未満までの間に毎月一定の金額(掛け金)を拠出し、投資信託や保険、定期預金などの金融商品を選んで資産を運用。
そして、運用した資産を、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができます。
60歳未満は掛金・運用した資産を受け取ることはできません。
iDeCoの加入資格
iDeCoは、以下の加入条件に該当する者が加入することができます。
| 加入区分 | 加入者 | 加入できない者 |
|---|---|---|
| 国民年金の 第1号被保険者 |
20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランスなど | 農業者年金の被保険者や国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方など |
| 国民年金の 第2号被保険者 |
60歳未満の厚生年金の被保険者(サラリーマンや公務員の方) | – |
| 国民年金の 第3号被保険者 |
20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方 | – |
2022年5月からiDeCoに加入できる年齢が原則65歳未満に拡大
従来の加入資格は60歳未満まででしたが、2022年5月から、
- 60歳以降も厚生年金に加入して働き続ける会社員や公務員などの第2号被保険者と
- 未払期間があり60歳以降も国民年金に任意加入している被保険者
は、iDeCoに加入できる年齢が原則65歳未満に拡大されました。
2022年5月から海外居住の方でもiDeCoに加入可能に
以前は、日本国内に住んでいる者しかiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していれば、海外居住の方でもiDeCoに加入できるようになりました。
2022年10月から企業型DCとiDeCoの同時加入要件の緩和
以前は、企業型DC(企業型確定拠出年金)を導入している企業に勤めている会社員は、iDeCoとの併用を認めることを企業年金の規約で定めない限り、iDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月からは、法改正で原則加入できるようになっています。
つまり、2022年の改正で殆どの人がiDeCoに加入できるようになりました。
iDeCoの掛け金の上限
iDeCoは、掛金月額5000円からスタートすることができ、1000円単位で設定できますが、加入者により、掛け金の上限が決まっています。
自営業者は、公的年金が手薄なので掛け金の上限が優遇されています。
| iDeCo加入者 | 掛金の上限(月額) | 掛金の上限(年間) |
|---|---|---|
| 自営業者 第1号被保険者 |
国民年金基金と 合わせて6万8,000円 |
国民年金基金と 合わせて816,000円 |
| 企業年金がない会社員 | 2万3,000円 | 276,000円 |
| 企業型DCに加入している 会社員 |
2万円 | 240,000円 |
| 企業型DCと 確定給付型年金(DB) に加入している会社員 |
1万2,000円 | 144,000円 |
| 公務員 | 1万2,000円 | 144,000円 |
| 専業主婦(夫) | 2万3,000円 | 276,000円 |
参考:自営業者・フリーランスにおすすめの国民年金基金!iDeCoよりお得?
iDeCoの受け取り方法
iDeCoの受け取り方には、
- 一時金
- 年金
- 年金と一時金の組み合わせ
の3種類があり、給付時には税金がかかる場合があります。
給付を一時金として一括で受取る場合は退職所得として取り扱われ、年金として分割して受取る場合は雑所得として取り扱われます。
iDeCoの受取り可能年齢
iDeCoは原則60歳から受け取れますが、60歳時点で加入から10年を経過していない場合は、通算加入者等期間に応じて、受け取り開始年齢が定められています。
| 加入期間 | 受け取り開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1ヵ月以上2年未満 | 65歳 |
尚、運用方法は一人一人異なりますので運用成績によって受け取る金額は一人一人異なります。
iDeCoは2022年5月以降、60歳以降も働いて厚生年金に加入している方や、60歳以降に国民年金の任意加入をしている方は65歳まで加入することができるようになりました。
そして、60歳以降でiDeCoに加入した場合は、加入から5年経過後にお金が受け取れるようになります。仮に61歳で加入した場合は最短で66歳が受け取り開始年齢となります。
75歳までは非課税で運用が可能
受け取り開始年齢に達したからといって、すぐに受け取る必要はありません。
iDeCoでは、60歳(65歳)を迎えて新たな掛金が拠出できなくなっても、70歳(2022年4月より75歳)までは非課税で運用を続けることができます。
iDeCoのメリット・デメリット
iDeCoに加入するメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
iDeCoのメリット
iDeCoは、掛け金の拠出、運用、受取の3つの段階で税制上のメリットがあります。
掛金の全額が所得控除の対象
iDeCoの最大のメリットは、掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される点にあります。
年末調整や確定申告を行うことで、サラリーマンなど他に収入があり税金を納めている方は、その所得や掛け金に応じて納めた税金が戻ってきます。
iDeCoは早く始めるほど節税効果が大きくなります。
運用益が非課税
通常、定期預金の利息や投資信託の運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの運用益はすべて非課税になります。
またその分の運用益もそのまま運用に回せるので、効率よく運用できます。
資産受け取り時にも節税
運用した資産は60歳から75歳までの間に、「一時金」「年金」「一時金と年金の両方」の3つのいずれかの形式で受け取ることになりますが、
- 一時金の形式で受け取れば「退職所得控除」
- 年金の形式で受け取れば「公的年金等控除」
が受けられ、節税になります。
60歳からでも受け取ることができる
公的年金の支給開始年齢は、原則65歳です。
定年退職が65歳未満であればその後65歳まで公的年金を受け取ることができません(但し、繰り上げ受給を申請すれば60歳からでも公的年金を受給することは可能です)。
従って、この間、収入がなければ貯蓄の切り崩しが必要になりますが、iDeCo(個人型確定拠出年金)など私的年金制度に加入しておくと、原則60歳からでも受け取ることができるため、公的年金受給までの空白の期間を補うことが可能です。
尚、加入者に万一があった場合、「障害給付金」と「死亡一時金」で受け取ることが可能です。
iDeCoのデメリット
元本は保証されていない
毎月支払う掛け金は、プロが運用しますが、運用の成果次第で、大きく増やすことができる可能性がある反面、掛けた金額の全てが戻ってくるとは限らないリスクもあります。
つまり、あくまでも投資ですので元本が保証されている訳ではありません。
60歳まで資産を引き出せない
iDeCoは、60歳までは積み立てた資産を引き出せません。途中で解約することも基本的に認められていませんので公的年金同様、老後までは使えないことを覚悟しておく必要があります。
尚、75歳までには年金(老齢給付金)の受け取りを開始しなければなりません。
終身年金ではない
国民年金や厚生年金は、終身年金(亡くなるまで年金が貰える)ですが、iDeCoは基本的に終身年金ではありません。
年金として受け取る場合でも、受給権が発生する年齢に達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。
手数料は自己負担
iDeCoの手数料は、大別すると、
- 加入手続きにかかる手数料と
- 運用中にかかる手数料
があります。
加入手続きにかかる手数料は、iDeCoの加入者が運営主体である国民年金基金連合会に対し、申込時に支払う手数料です。一律2,829円です(2022年8月現在)。
運用中にかかる手数料には、どの金融機関でiDeCoに加入してもかかる国民年金基金連合会に支払う月額105円と、運営管理機関に対して支払う手数料(0円~500円ほど)があります。
その他にも給付を受け取る際にかかる場合や金融機関を変更する場合にも手数料がかかります。
iDeCoへ加入するには
iDeCoへの加入の申込み手続きはiDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関と言われています)経由で国民年金基金連合会に申し込みます。
運営管理機関が提示する運用商品(預貯金、投資信託、保険商品等)から自分の運用方針に沿ったものを選びます。
尚、初回掛金入金後約3ヵ月を経過しても運用商品の指図がない場合は、金融機関が指定する運用商品(デフォルト商品)が自動的に購入されます。
iDeCoの掛金は、月々5,000円以上1,000円単位で、ご自身の加入資格に沿った上限額の範囲内で設定できます。
掛金の額は、1年に1度変更することができますので、自分の状況の変化に合わせて、掛金額の増減をすることも可能です。
おすすめの運営管理機関
| おすすめのiDeCo運営機関 | 内容 |
|---|---|
| 松井証券 | 運営管理手数料が0円 低コスト商品40種類 創業100年の歴史と実績 |
| 運営管理手数料が0円 スマホでいつでもどこでも運用状況をチェック可能 運用残高に応じて毎月au WALLETポイントがもらえる。 |
|
| 楽天証券のiDeCo | 運営管理手数料が0円 商品ラインナップ厳選の32本 |
まとめ
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金とは別にそれにプラスして給付を受けられる私的年金制度の一つです。
60歳(一部65歳)までの間に毎月一定の掛け金で投資信託や保険、定期預金などの金融商品を選んで資産を運用し、60歳以降に運用した資産を老齢給付金として受け取るというものです。
iDeCoへの加入の申込み手続きはiDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関と言われています)経由で国民年金基金連合会に申し込みます。
運営管理機関が提示する運用商品(預貯金、投資信託、保険商品等)から自分の運用方針に沿ったものを選びます。
毎月支払う掛け金は、プロが運用し、運用の成果次第で、大きく増やすことができる可能性がある反面、掛けた金額の全てが戻ってくるとは限らないリスクもありますが、掛金の全額が所得控除の対象だったり、運用益が非課税といったメリットがあるため人気があります。
