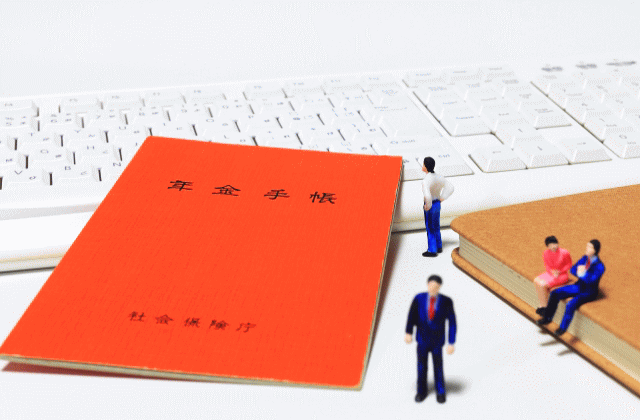国民年金基金という制度をご存じでしょうか。
ときどきテレビでもCMが流れていますので聞いたことがある方も多いと思います。
ここでは、国民年金基金とはどういう制度か?自営業者やフリーランスに国民年金基金をおすすめする理由、国民年金基金はiDeCoよりお得なのか?と言った点について解説しています。
国民年金基金は国民年金法にもとづく公的年金
国民年金基金は、国民年金法にもとづく公的年金です。
会社員や公務員は、国民年金にプラスして厚生年金や企業年金に加入していますが、自営業やフリーランスの人は、基本、国民年金だけにしか加入していません。
その結果、厚生年金や企業年金に加入していた会社員であれば、支給される年金額は月額平均16万円ほどありますが、自営業やフリーランスの人は国民年金を満額支払っても支給される年金額は月額6.5万円と会社員や公務員の半分もありません。
そこで、自営業者やフリーランスの人にも将来の年金受給額を増やす方法として設けられている制度の一つが、国民年金基金の制度です。
国民年金基金の制度は、国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担います。
国民年金基金は何と言っても終身年金(一生涯受け取れる)がある点が魅力です。
特に人生100年時代と言われるようになった近年は、国民年金基金に人気が出てきています。
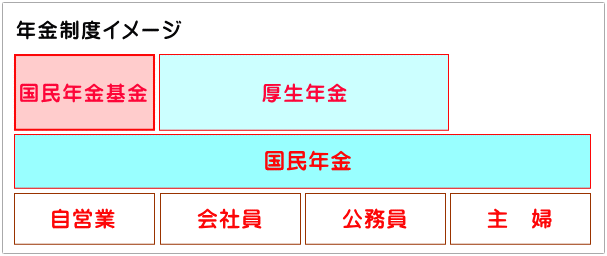
国民年金基金制度の概要
確定給付型の公的年金
国民年金基金は、確定給付型なので、契約した時点で、納める年金額(掛金)も将来給付される年金額も確定します。
国民年金基金への加入は任意ですが、加入後は途中で任意に脱退することはできません。
また、年金なので契約した年齢になるまではお金が受け取れません。
例えば、会社に就職するなどして第1号被保険者でなくなった場合は脱退できますが、それまでに納付した掛金はすぐには返納してもらえず掛金に応じて年金という形でのみ受け取れます。
但し、加入者が死亡した際には遺族一時金として一時金を受け取ることはできます。
国民年金基金へ加入できる人・できない人
国民年金基金へ加入できる人
国民年金基金は、20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、また、学生や無職も方でも国民年金の第1号被保険者であれば加入できます。
また、国民年金法の一部改正により、60歳以上65歳未満の方でも国民年金に任意加入している方は加入できるようになりました。
参考:国民年金の任意加入制度で貰える年金額を増やす
国民年金基金へ加入できない人
厚生年金保険に加入している会社員(国民年金の第2号被保険者)や厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)、また、農業者年金加入者と国民保険料免除者は国民年金基金に加入できません。
また、国民年金基金に加入した方が次のいずれかに該当したときは加入資格を喪失します。
- 60歳になったとき
- 国民年金の任意加入被保険者ではなくなったとき
- 国民年金の保険料を免除されたとき(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)
- 会社員になって国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
- 会社員の被扶養配偶者になったとき(国民年金の第3号被保険者となったとき)
- 職能型基金に加入している場合は該当する事業または業務に従事しなくなったとき
- 農業者年金の被保険者になったとき
- 加入者本人が死亡したとき
尚、加入資格を喪失した場合でも、支払った掛金は途中で引き出すことはできず、将来、年金として支給されます。
年金受給前に加入者が死亡した場合は、加入時年齢、死亡時年齢および死亡時までの掛金納付状況に応じた遺族一時金が支給されます。
保証期間中に年金受給者が死亡した場合は、残りの保証期間の年金を支給されるための年金原資相当額が遺族一時金として支給されます。
終身年金・確定年金を自分で選べる自由なプラン設計
国民年金基金は、限度額(月額68,000円)の範囲内で、
- 終身年金か確定年金かの「給付の型」と、
- それぞれへの「加入口数」
を選択することで、掛金と将来受け取ることができる年金額と期間を決めることができます。
給付の型
給付の型には、
- 終身年金としてのA型とB型
- 確定年金(受給期間が決まっている)としてのⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型
の7種類があります。
加入口数
加入口数は文字通り加入する口数で、例えば、
- 65歳から終身でもらえる終身年金A型に1口
- 60歳から10年かけてもらう確定年金Ⅳ型に3口
といったように掛けることができます。
1口目は、終身年金A型、B型のいずれかを選択する必要があります。
2口目以降は、終身年金のA型、B型のほか、受給期間が定まっている確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型から選択します。
1口目は途中で減額したり、型を変更(A型からB型、B型からA型)することはできませんが、2口目からの給付の型と口数は、途中で増減することができます。
尚、終身年金のA型と確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型は、保証期間があり、年金受給前または保証期間中に亡くなった場合、遺族の方に一時金が支給されます。
国民年金基金は、iDeCoと異なり、貰える年金額も予めわかるため自分の人生設計に合わせた掛け方が可能です。
万が一の時は家族に一時金支給あり
万が一、加入者が年金を受け取る前に亡くなったときは、加入時年齢、死亡時年齢および死亡時までの掛金納付状況に応じた遺族一時金が家族に支給されます(加入型B型を除く)。
また、保証期間中に年金受給者が死亡した場合も、残りの保証期間の年金を支給されるための年金原資相当額が遺族一時金として支給されます。
国民年金基金の掛金の限度額
国民年金基金の掛金の限度額は、月額68,000円(年間816,000円)です。
もし、iDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入している場合は、その掛金と合計して月額68,000円以内となります。
国民年金基金の最低の掛金額は、加入時の年齢や性別により異なります。
国民年金基金の掛金は税制優遇の対象
国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として全額所得控除となるため、所得税や住民税を支払っている人には節税対策になります。
さらに、国民年金基金は、年金を受け取る際にも国民年金や厚生年金等の年金と併せて公的年金等控除の対象となりますし、遺族一時金は全額非課税となります。
掛金の納付の仕方
国民年金基金の納付方法には、
- 毎月、掛金を納付する方法と
- 1年分を前納する方法
があります。
毎月、掛金を納付する場合、掛金は、毎月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に指定の銀行口座から引き落とされます。
前納する場合は、毎年4月分から翌年3月分までの1年分の掛金を一括して6月1日に納付します。
前納する場合は、0.1ヵ月分の掛金が割引されます。
国民年金基金はどれくらいのリターンが見込めるのか
実際、掛金に対してどれくらいの年金額(リターン)が見込めるのか気になるところです。
2021年7月現在の予定利率は1.5%とされており、申し込み時の予定利率で最後まで続きます。
公式サイトの年金額シミュレーションで調べてみます。
課税所得200万円の40歳男性 1口目:終身年金B型、2口目:終身年金B型に加入
上記のモデルケースでシミュレーションをしてみると、掛金は月額16,060円になります。
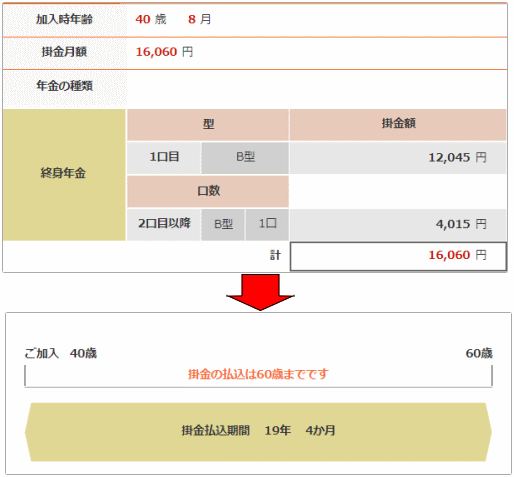
60歳までの掛金払込期間は19年4ヵ月になりますので、掛金の合計は3,725,920円となります。
これに対して受け取る年金額はというと、65歳から年額244,800円ほど。
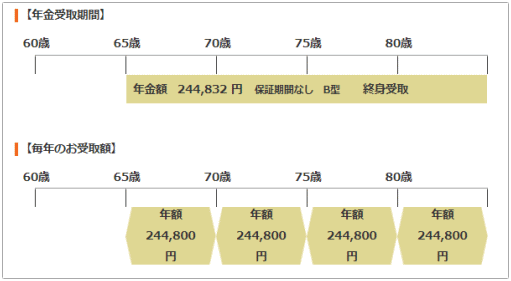
日本人男性の平均寿命である81歳まで生きるとすると、年金支給額は16年で3,916,800円となり、掛金よりも190,880円多くなります(3,916,800円 – 3,725,920円)。
そして、それ82歳以降は丸々お得ということになります。
さらに、掛金を支払っている時の課税所得が200万円であれば、所得税と住民税(10%で計算)で年間およそ38,948円軽減されます。
60歳まで働くとすると、19年ほどで74万円の節税となります。
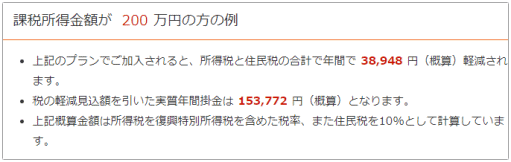
81歳まで生きるとすると、減税額も計算に入れると、実質298万円ほど支払って390万円の年金を受け取ることになりますので、随分お得になることがわかります。
平均寿命より早く亡くなれば年金受給額が掛金よりも下回ることがありますが、長生きすればするほど年金受給額は掛金より多くなります。
終身年金というのが国民年金基金の最大の魅力ですなので安心して老後を迎えられます。
何歳まで生きればお得になるのか?自分の場合はどうなのか、気になる方は、是非、公式サイトでシミュレーションしてみて下さい。
参考:国民年金基金
自営業者・フリーランスにおすすめの国民年金基金
私事ですが、20年近く前に会社を辞め、厚生年金の加入資格を失いました。
国民年金だけでは老後の年金に不安があったので、自営業を始めて2~3年後に税理士が勧めるまま国民年金基金に加入しました。
以降は、50歳でアーリーリタイアした後も納め続けています(↓私本人のものです)。
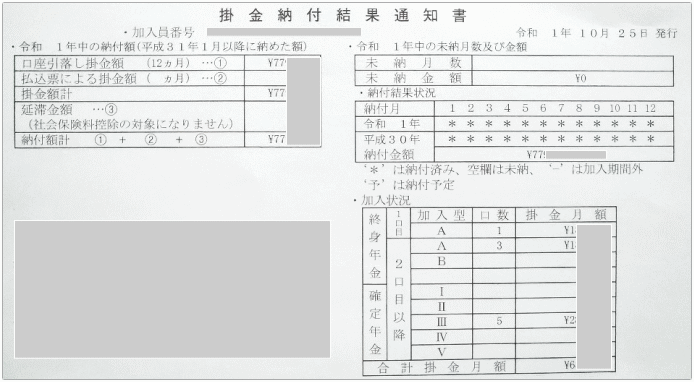
掛金は月額65,000円(年間78万円ほど)ほどと大金ですが、自営業をしていた10年間は、この分(毎年78万円ほど)の所得控除を受けることができました。
結果、年間2割にあたる16万円の減税効果があったとしたら、10年でおよそ160万円(80万円×20%×10年)ほど節税している計算になります。
また、アーリーリタイアした後もネットなどからの収入が年間150万円くらいありますが、この社会保険料控除により、納める所得税や住民税を殆どゼロで済ませることができています。
このように、国民年金基金は節税効果がある点もおすすめですが、何よりもおすすめな点は、終身年金である点です。
万が一(とも言えなくなってきましたが)90歳、100歳と生きてしまったら有期の年金では生活が破綻しかねません。
その点、終身であれば、国民年金と合わせて一生涯一定の年金を受け取ることができます。
つまり、国民年金基金は、長生きリスクに対応した数少ない年金制度の一つと言えるのです。
結果、私の場合、60歳までには、20年近く納めることになり、60歳から月額5万円ほど、65歳からは老齢年金と国民年金基金分を合せて月額18万円ほどの年金が貰える予定です。
例えば、アフィリエイトやブログで広告収入を得ている方など自営業をされている方で未加入の方は加入を検討してみてはどうでしょうか。
国民年金基金とiDeCoはどちらがお得か?
最後に国民年金基金とiDeCo、どちらがいいかという問題について考えてみます。
両者はよく比較されます。
両者の違いは簡単に整理すると以下の通りです。
| 比較項目 | 国民年金基金 | iDeCo |
|---|---|---|
| 年金制度 | 確定給付型 加入した期間と掛金などに基づいてあらかじめ将来の給付額が決められている |
確定拠出型 加入者が拠出した掛金と選んだ商品の運用収益(運用益は非課税)との合計額をもとに給付額を決定 |
| 年金支給 | 基本的に終身年金 基本的に60~65歳から給付開始 |
基本的に有期年金 60~65歳の間に給付開始 |
| 税制上 | 掛金は全額所得控除可能で、受け取り時も公的年金等控除の対象になる | |
| 掛金と脱退 | 国民年金基金とiDeCoは併用可能で、掛け金の上限は両方合わせて68,000円。どちらも一度加入すると任意に脱退することができない | |
| 加入資格 | 20歳以上65歳未満までの第1号被保険者 | 20歳から60歳以下の国民年金に加入する全ての人 |
| 補足 | インフレに対応していない。インフレで貨幣価値が下がっても貰う金額は決まっているリスクあり | 運用で元本割れ(損)をするリスクあり |
両者の最も大きな違いは、国民年金基金が確定給付型で基本的に終身年金であるのに対して、iDeCoは確定拠出型で基本的に有期年金である点です。
確定拠出型のiDeCoは運用次第で大きく増やすことができますが、元本を割り込むリスクもあります。また、基準価額が上がったり下がったりで一喜一憂することもあると思います。
一方、国民年金基金は、第1号被保険者と加入者が限定されますが、掛金で年金給付額が決まりますし、終身が選べますので、将来設計も立てやすくなります。
どちらがいい、お得かというのは、運用が終わって年金を貰ってみるまでわかりません。
両者は併用可能ですので、限度額の範囲内で掛金を分散するという手もあります。
尚、iDeCoにも終身年金の商品(個人年金保険)があるにはありますが、予定利率では国民年金基金が断然有利です。
国民年金基金への加入の仕方
国民年金基金への加入資格があり、加入を希望する方は、国民年金基金加入申出書を提出して申し込むことができます。
国民年金基金加入申出書は、国民年金基金公式サイトの「手続きの流れを見る」⇒「ご加入の流れ」から資料請求をして取り寄せることができます。
参考:国民年金基金
国民年金基金加入申出書に必要事項を記入して各支部へ送付すると、受付・登録後、加入員証が郵送されてきます。
原則として加入2ヵ月後から掛金の引き落としが開始されます。
尚、国民年金基金に加入する方は。基金が付加年金を代行しているため月額400円の国民年金の付加保険料を納める必要がなくなります。
まとめ
以上、国民年金基金とはどういう制度か?自営業者やフリーランスに国民年金基金をおすすめする理由、国民年金基金はiDeCoよりお得なのか?と言った点について解説してきました。
両者とも破綻や損するリスクはゼロとは言い切れませんが、これは他の公的年金も同じです。
しかし、万が一、破綻となったとしても国民年金基金は公的年金なので、何らかの救済措置が期待でき、7~8割は貰えるのではないかと考えています。
十分な貯蓄のある人ならともかく、そうでない人は何も対策を講じなければ老後は安心して生きていけない訳ですから何らかの年金制度を信じて加入するしかないと考えます。
国民年金基金は、掛ける時点で給付される年金額がわかりますし、終身が基本ですので人生設計も立てやすくなります。自営業者・フリーランスの方におすすめです。