将来、受け取れる年金の額を増やすにはどういう方法があるでしょうか?
簡単な方法があるのに知らずに損をしていることはないでしょうか?
ここでは、若い方はもちろん、60歳以上でも年金を増やす10の方法について解説しています。
年金を増やす10の方法
高齢任意加入(任意加入制度)の活用
高齢任意加入制度とは、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480ヵ月未満の人が、本人の申し出により60歳以上65歳未満の5年間に、納付月数480ヵ月まで国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。
2017年8月1日から老齢基礎年金の受給資格(国民年金保険料の支払い)の期間が、25年以上から10年以上に短縮されました。
これにより、国民年金保険料の納付または免除期間が120ヶ月(10年)以上あれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
また、老齢基礎年金を満額(年間約78万円)を受給するためには、国民年金の加入義務である20歳から60歳になるまでの40年間(480ヶ月)国民年金保険料を納付している必要があります。
しかし、中には、10年間も納めていない人もいますし、学生だったり、仕事をしていない期間があったり、産前産後に休職したりなどの理由で、60歳までに未加入期間がある人もいます。
そういう人たちのために設けられている制度が、高齢任意加入制度です。
この制度を利用することで、10年納めるという条件をクリアして老齢基礎年金を65歳から貰えるようにしたり、貰える老齢基礎年金を増やすことができます。
任意加入が可能な条件などは下の記事で詳しく解説しているのでそちらを参照して下さい。
国民年金保険料の追納
国民年金保険料の追納とは、言葉的には、上記の高齢任意加入制度と似ていますが、両者の内容は全く異なります。
国民年金保険料の追納は、国民年金保険料の免除や納付猶予、また学生納付特例を受けた人を対象として設けられた制度です。
例えば、収入が減ったり、失業したりして、国民年金保険料の免除や納付猶予を受けたり、また、学生時代に支払う余裕がなく学生納付特例を受けたりした場合は、年金の受給資格期間としては計算されますが、免除されたり納付猶予を受けた分は貰える年金額には反映されません。
つまり、納めていない分、貰える年金額が少なくなります。
しかし、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、追納という救済措置があり、後に追納することで、その分、貰える年金額が多くなります。
追納は、一括払いと分割払いから選択できます。
但し、追納できる期限は、遡ること最大10年前までです。保険料の免除または猶予、学生納付特例を受けても10年以上経過すると追納制度を利用することはできなくなります。
また、3年以上前の年金保険料を追納する場合は経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
国民年金保険料の追納が可能な条件等は下の記事で詳しく解説しています。
付加年金への加入
自営業者や無職の方は付加年金で年金を増やすことができます。
付加年金は、自営業者などの第1号被保険者ならびに任意加入被保険者の老齢基礎年金の上乗せとして用意してある制度です。
毎月の国民年金保険料に400円の付加年金保険料を上乗せして納めることで、将来受給する老齢基礎年金が、年間「付加年金保険料を納付した月数×200円」増やせます。
例えば、付加年金保険料を10年間(120ヵ月)納付していた場合、老齢基礎年金に加算される金額は、年間24,000円(120ヵ月×200円)です。
支払った金額は、48,000円(400円×120ヵ月)ですので、2年で元が取れる計算になります。
死亡するまで支給されますので、3年目以降はまるまるお得になります。
上記の高齢任意加入の支払いに付加保険料をプラスして納めることもできます。
尚、国民年金基金に加入している方は、その中に付加年金も含まれていますので付加保険料を納める必要はありません。
加給年金・振替加算の申請
加給年金とは、老齢厚生年金を受給できる夫(又は妻)に、生計を維持している配偶者や子供がいる場合に老齢厚生年金とは別に支給される年金のことです。
生計を維持している者が配偶者の場合は、さらに配偶者特別加算額が加算されます。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳に到達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者または結婚していない18歳未満の子どもがいる場合は、申請することで加給年金が貰えます。
配偶者が65歳になるまで、年間40万円近い年金がプラス支給されますので、条件をクリアしている場合は忘れずに申請しましょう。
振替加算は、加給年金が支給されなくなったとき(配偶者が65歳になったときや子どもが18歳に到達する年度の末日になったとき)、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合に一定の条件を満たしていると貰えるお金です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)とは、個人が投資信託や預金・保険などの金融商品を選び、決まった金額を積み立てながら運用し、後に年金として受け取る私的年金制度です。
掛け金は、月々5,000円から1,000円単位で、下記の掛金を上限に、自営業や会社員、主婦等など、殆どの人が加入できます。
| iDeCo加入者 | 掛金の上限(年間) |
|---|---|
| 自営業者 | 国民年金基金と合わせて816,000円 |
| 会社員 | 276,000円 |
| 企業年金のある会社員 | 144,000円 |
| 公務員 | 144,000円 |
| 専業主婦 | 276,000円 |
毎月支払う掛け金の全額が所得控除の対象となったり、運用益が非課税となったり、また、資産受け取り時も節税ができるなどのメリットがあります。
但し、掛金は、プロが運用するものの、運用の成果次第で、大きく増やすことができる可能性がある反面、元本割れするリスクもあります。
iDeCoへの加入の申込み手続きは、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関と言われています)経由で国民年金基金連合会に申し込むことで加入できます。
iDeCoについては、下記のページで詳しく解説しています。
国民年金基金への加入
自営業者や無職の方は国民年金基金で年金を増やすことができます。
国民年金基金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者のための公的年金です。20歳以上60歳未満の自営業者とその家族などの国民年金の第1号被保険者であれば加入できます。
会社員などが加入する厚生年金の代わりとして活用できます。
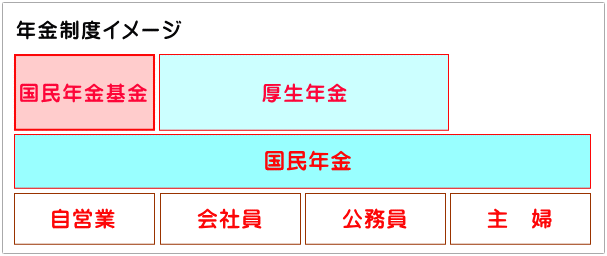
国民年金基金の掛金の限度額は、月額68,000円(年間816,000円)です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入している場合は、その掛金と合計して月額68,000円以内となります。
終身年金か確定年金かの「給付の型」と、それぞれへの「加入口数」を選択することで、掛金と将来受け取ることができる年金額と期間が決まります。
従って、iDeCoと異なり、年金額も予めわかるためより確実な人生設計が立てられます。
また、国民年金基金の掛金は、全額所得控除となるため、所得税や住民税を支払っている人には節税対策になりますし、年金を受け取る際も国民年金や厚生年金等の年金と併せて公的年金等控除の対象となります。
国民年金基金は、公式サイトの「手続きの流れを見る」⇒「ご加入の流れ」から資料請求をし、国民年金基金加入申出書を提出して加入することができます。
国民年金基金については、以下のページで詳しく解説しています。
個人年金保険への加入
個人年金保険とは、民間の保険会社の個人年金保険に加入することで、公的年金などでは不足する部分を自分で用意する私的年金のことです。
個人年金保険には、主に「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3つの種類があります。
保険料を納めることで、契約時に定めた時期から、年金または一時金として保険金を受け取ることができます。
所定の条件を満たせば、所得税や住民税の負担を軽減できる個人年金保険料控除が受けられたり、そうでなくても、一般の生命保険料控除として控除を受けることができます。
途中で解約しなければ元本が保証されているものが殆どですが、年金を受け取るまでに保険会社が破綻すると年金が大きく減少する可能性があります。
銀行や保険会社などで商品の説明を受けて加入することができます。
繰り下げ受給を申請
公的年金は、原則65歳から支給が開始されますが、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに支給の開始時期を遅らせることで、受給する年金額を増額させることができます。
このように、公的年金の支給開始時期を遅らせることを、繰り下げ受給といいます。
受給開始時期を1ヶ月繰り下げるごとに年金額は0.7%ずつ増額させることができ、70歳までの最長5年間繰り下げると、70歳から受給する年金額は65歳で受け取る年金に42%(0.7%×60ヶ月)増額した年金額になります。
尚、現在は最大70歳までしか繰り下げ受給できませんが、法改正で2022年4月から最大75歳まで繰り下げることができるようになります(75歳まで繰り下げた場合は、84%増)。
そして、仮に受給開始年齢を70歳まで繰り下げた場合は、81歳くらいまで生きれば、受け取る金額が65歳から受け取った場合の金額を追い越してしまいます。
健康に自信があり長生きしそうな人で、70歳まで貯蓄や収入だけで生活できる人は、繰り下げ受給を選択した方が生涯で受け取る年金額は65歳から貰うよりも多いかもしれません。
但し、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、年下の配偶者や子どもがいる場合は、加給年金が貰える場合があり、年金の繰り下げ受給をした場合は、その繰り下げ待機中は加給年金は支給されないことに注意が必要です。
また、繰り下げ待機中に年金受給者が亡くなったときは、家族に支給される遺族年金は、夫が65歳時点で貰うはずだった本来の年金額をもとに計算されて支給されます。
繰り下げ受給で遺族年金が増えることはありません。
寡婦年金または死亡一時金の申請
寡婦年金と死亡一時金は、遺族年金が、特定の条件下でしか支給されない自営業者など第1号被保険者に救済措置として支払われる年金です。
受給要件を満たしている妻や遺族は、申請期限までに申請すれば、寡婦年金または死亡一時金のいずれかを受け取ることができます。
詳細は下の記事でまとめています。
60歳以降も厚生年金に加入して働く
国民年金は20歳から60歳までの加入で老齢基礎年金額の上限は決まっていますが、厚生年金は60歳以降70歳未満まで加入することができるため、その分、老齢厚生年金の額は増えます。
実際、定年退職年齢の延長で65歳から70歳まで働いている人の方が多くなってきているため、仕事に割く時間は犠牲にしなければなりませんが、年金受給額は増え、さほど老後の心配をしなくていい時代になっていくと思われます。
2022年10月の改正では、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入できる条件が、大きく緩和されるので、パート感覚で勤めていても老齢厚生年金の額を増やすことが出来るようになります。
まとめ
以上、年金を増やす10つの方法を解説してきました。
それぞれの方法には加入条件があります。
| 年金を増やす方法 | 加入条件など |
|---|---|
| 高齢任意加入 | ・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方 ・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480ヵ月未満の方 ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方 ・任意加入手続時に厚生年金保険、共済組合等に加入していない方 |
| 国民年金保険料 の追納 |
・国民年金保険料の免除や納付猶予を受けたり、学生納付特例を受けた人 ・追納できるのは最大過去10年分まで ・過去2年以内に未納の国民年金保険料がある場合 |
| 付加年金への加入 | ・国民年金保険料を納付している第1号被保険者 ・20歳以上60歳未満 ・65歳以上の人を除く任意加入被保険者 ・国民年金基金の加入者は加入不可 |
| 加給年金・振替加算 | <加給年金> ・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある ・65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者または結婚していない18歳未満の子どもがいる ・配偶者は65歳未満である <振替加算> ・昭和41年4月1日までの間に生まれていること ・妻(夫)の厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること |
| iDeCo | ・60歳未満の方(自営業者・主婦は20歳以上)2022年5月からは65歳未満に ・国民年金保険料を納付している ・掛金の上限の細かい定めあり |
| 国民年金基金 | ・国民年金保険料を納付している第1号被保険者 ・20歳以上60歳未満 ・60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者および海外居住者で国民年金の任意加入被保険者の方 |
| 個人年金保険 | ・20歳以上60歳未満の方なら誰でも加入可 |
| 繰り下げ受給 | ・年金の受給資格のある方 |
| 寡婦年金または 死亡一時金 |
・寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上の夫が年金を受け取る前に亡くなったときにその夫と10年以上継続して婚姻関係あり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻 ・死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が36ヵ月以上ある人が年金を受け取る前に亡くなったときに生計を同じくしていた遺族 |
| 60歳以降も厚生年金 に加入して働く |
・厚生年金は60歳以降70歳未満まで加入することができるため、その分、老齢厚生年金の額は増えます。2022年10月の改正では、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入できる条件が、大きく緩和されるので、パート感覚で勤めていても老齢厚生年金の額を増やすことが出来るようになります。 |
ちなみに、自営業時代が長かった筆者は、40歳で国民年金基金に加入し、50歳でアーリーリタイアした後も国民年金基金の保険料を納付しています。
また、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数は480ヵ月未満なので高齢任意加入を利用する予定ですし、健康状態を見て夫婦ともに繰り下げ受給を申請するつもりです。
