ここでは、独立も可能な資格と言われている「公認心理師」とはどういう資格か、試験の内容や難易度、また独立が可能なのかなどを解説しています。
公認心理師とは?
公認心理師は、国民の心の健康の保持増進を適正に業務遂行できるように2017年9月に新しく作られた心理系カウンセラーの資格としては唯一の国家資格です。
心理系カウンセラーの資格としては、民間資格の臨床心理士が有名ですが、新たに公認心理師という国家資格が誕生したことによって臨床心理士の立ち位置は変わってくるかもしれません。
公認心理師の業務は、保健医療、福祉、教育その他の分野において専門的知識及び技術をもち、公認心理師の名称を用いて、
- 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する
- 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う
- 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う
- 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う
こととされています。
2018年12月に第1回目の公認心理師試験が開始されたばかりの新しい資格なため、活躍する場所の実例はさほど多くありませんが、民間資格である臨床心理士と業務の内容が類似しているため、臨床心理士と同じく、スクールカウンセラーや医療機関での心理カウンセラー、民間企業での産業カウンセラーなど、幅広い場所での活躍が期待できます。
公認心理師は、国家試験に合格後、一般財団法人日本心理研修センターに所定の事項についての登録申請を行うことで、なることができます。
尚、公認心理師は名称独占資格であるため、公認心理師以外の者がその名称又は心理師という文字を用いた場合、違反者には罰則が与えられます(心理カウンセラーといった名称は資格が無くても名乗ることが可能です)。
公認心理師は、国家資格のため今後は、必置資格として認定される可能性もあります。
| 美容師 | 評価 |
|---|---|
| 受験資格 | あり |
| 就職・転職に役立つか | |
| 定年後の再就職に役立つか | |
| 独立に役立つか | |
| 難易度 | やや難しい |
公認心理師試験の概要
公認心理師試験は、一般財団法人 日本心理研修センターが実施します。
受験資格
公認心理師の受験資格は、以下の通りです。
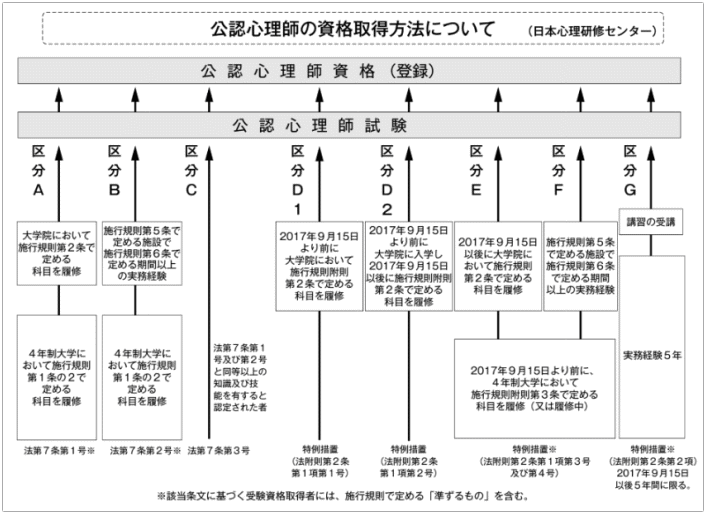
引用元:一般財団法人 日本心理研修センター
- 区分A:4年制大学で指定の科目を履修後、大学院で指定の科目を履修
- 区分B:4年制大学で指定の科目を履修後、特定の施設で施行規則で定める期間以上の実務経験
- 区分C:外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、外国の大学院において心理に関する科目を修了
した者というのが基本ですが、区分Dから区分Gまでの経過(特例)措置もあります。
経験年数だけで受験資格を与えられる区分Gのルートは大卒、高卒でも受験できますが、2022年までの時限措置です。
区分Bと区分Fの実務経験が認められる施設は、公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設一覧に定められています。
このように公認心理士には厳しい受験資格があります。
受験資格が必要ない国家資格は下の記事にまとめていますので参考にして下さい。
試験日時
例年、2月から3月の間から3月から4月までに受験申込受付が開始され、試験が5月から6月の日曜日に実施されます。午前と午後に分かれて2時間づつ、計4時間(240分)で行われます。
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県で実施されます。
試験の方法と内容
試験の方法
全問マークシート方式(4択または5択)で150~200問程度。
一般問題と事例問題(ケース問題)が出題され、事例問題に大きなウェイトが置かれています。
試験の内容
公認心理師としての業務を行うために必要な知識及び技能の到達度を確認することに主眼を置いて出題されます。
- 公認心理師としての職責の自覚
- 問題解決能力と生涯学習
- 多職種連携・地域連携
- 心理学・臨床心理学の全体像
- 心理学における研究
- 心理学に関する実験
- 知覚及び認知
- 学習及び言語
- 感情及び人格
- 脳・神経の働き
- 社会及び集団に関する心理学
- 発達
- 障害者(児)の心理学
- 心理状態の観察及び結果の分析
- 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)
- 健康・医療に関する心理学
- 福祉に関する心理学
- 教育に関する心理学
- 司法・犯罪に関する心理学
- 産業・組織に関する心理学
- 人体の構造と機能及び疾病
- 精神疾患とその治療
- 公認心理師に関係する制度
- その他(心の健康教育に関する事項等)
受験手数料
28,700円
公認心理師試験の難易度
合格基準
合格基準は、正答率が60%程度以上です。
合格率
2022年に実施された第5回公認心理師試験は、受験者数が33,296人、合格者が16,084人で合格率は48.3%でした。
今後は40~50%程度で推移していくと思われます。
公認心理師試験の難易度
難易度: やや難しい
合格までの学習時間の目安:600時間
合格率は、50%前後とやや高めですが、ハードルの高い受験資格がある中での合格率であるため、決して易しい試験ではありません。
公認心理師として独立開業が可能か
公認心理師として独立が可能か、という視点でみてみると、類似した資格である臨床心理士がどうなのかが参考になります。
臨床心理士は、心理カウンセラーとして独立することが可能ですし、実際、多くの人が独立して活躍しています。むしろ、就職する場所を探す方が厳しいという声もあります。
しかし、臨床心理士でも資格を取得したからといってすぐに独立する人は稀です。
独立する場合でも経験を通して専門知識を深めたり、様々なケースに対応できるだけの力を身に着けて独立する人が殆どです。
従って、公認心理師も資格取得後、一定の経験を積んである程度の自信をつけて独立ということになるでしょう。カウンセリングの性質上、20代、30代の若い方より人生経験豊かなシニアの方のほうが独立して成功しやすいかもしれません。
また、公認心理師は、心理カウンセラー系の資格の中で唯一の国家資格ですので、独立後は、国家資格であることを活かして営業活動ができます。唯一、心理師という名称も使えます。
独立して成功できるか、安定した収入を得ることができるか、は、本人次第です。
独立して成功するためには、やはりクライアントを増やす努力は欠かせません。
現在は、相談先を探す時、まずはインターネットで検索しますので、自分のブログやカウンセラーのホームページを作成して集客することが最も有効な営業となります。
自分のサイトを作ることで信用にも繋がります。
また、関連するセミナーの講師や執筆活動をこなすことで口コミも広がりクライアントの獲得に繋がりますので積極的に受けるようにしたいものです。
開業は自宅の一室をカウンセリングルームにしてもいいですし、カウンセリングの依頼を受けた時だけ会議室を借りるというスタイルでもいいと思います。
インターネットで集客をして電話相談、メール相談という形でも収入を得ることが可能です。
年間の自殺者3万人といわれ、学校や職場、家庭、地域など、さまざまな場所で心の問題を抱える人が多い現代社会において、公認心理師への需要は今後増々高まってくることが予想されますので、独立して安定した収入を得ることはさほど難しいことではないと思われます。
公認心理師以外の独立が可能な資格については、下の記事でまとめていますので参考にして頂ければと思います。
公認心理師としては定年後に独立することは可能か
公認心理師は、心理カウンセラーです。
カウンセリングを行う性質上、若い方より人生経験・社会経験豊かな定年退職したシニアの方への需要が多いと言えることから、定年後に公認心理師として独立することは十分に可能です。
また、男性だけでなく女性も活躍できます。
自宅の一室をカウンセリングルームとして使えば開業費用も少なくて済み、失敗するリスクも少なくてすみます。インターネットを使った相談やセミナー講師としての需要もあります。
公認心理師以外の定年後に役立つ資格や受験資格のない資格は、下の記事でまとめていますので参考にして頂ければと思います。
