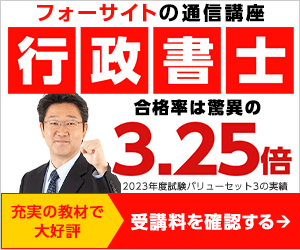ここでは、行政書士とはどういう職業か、行政書士は独立開業におすすめか?また、試験の難易度や合格率などを解説しています。
行政書士とは?
行政書士とは、行政書士法により誕生した国家資格です。
他人の依頼を受け報酬を得て、
- 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」
- その書類の申請(提出手続き)を代わりに行う「許認可申請の代理」
- 官公署に届ける書類の作成についてクライアントからの相談を受けアドバイスを行う「相談業務」
などを行います。
「官公署に提出する書類」とは、例えば、自動車に関する申請書や法人設立に関する申請書、土地利用に関する申請書などがあり、「権利義務に関する書類」には、各種契約書のほか遺産分割協議書、内容証明などがあります。
「事実証明に関する書類」とは、会計帳簿や貸借対照表、損益計算書、実地調査に基づく各種図面類、取締役会議事録などが該当します。
例えば、遺言においては、遺言書の起案・作成の支援、遺産相続においては遺産分割協議書等の作成・相続財産の調査・相続人の確定調査などを行います。
これらの業務は原則として行政書士の資格がなければ行えず(独占業務)、職務上、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる八士業の一つです。
但し、社会保険労務士とは違い、会社員の立場として行政書士会に登録することができないため、企業に勤める場合は、その企業内で行政書士として働くことはできません。
行政書士は、独占業務があり、比較的少ない資金で開業できることや自分のペースで仕事ができることから独立開業を目指す方に人気があります。
| 行政書士 | 評価 |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 就職・転職に役立つか | |
| 定年後の再就職に役立つか | |
| 独立に役立つか | |
| 難易度 | やや難しい |
行政書士になるには?
次に該当する者が行政書士となる資格を有します。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
これに加えて、公務員には「特認制度」があり、行政書士試験に合格しなくても条件を満たせば資格が得られます 。
行政書士として業務を行うには、都道府県の行政書士会に必要書類を提出して、行政書士会へ登録する必要があります。
尚、行政書士として登録ができるのは20歳以上です。
特定行政書士とは?
行政書士法が2014年に改正され、特定行政書士が誕生しました。
特定行政書士とは、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる行政書士です。
以下の全18時間の研修を受け、試験に合格することで特定行政書士になることができます。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 行政法総論 行政手続制度概説 |
各1時間 |
| 行政手続法の論点 行政不服審査制度概説 行政不服審査法の論点 行政事件訴訟法の論点 |
各2時間 |
| 要件事実・事実認定論 | 4時間 |
| 特定行政書士の倫理 | 2時間 |
| 総まとめ | 2時間 |
| 合計 | 18時間 |
試験の合格率は7割程度。難関ではありませんが、受験者は全て行政書士なのに3割が不合格となる試験ですから油断すると不合格になります。
行政書士試験の概要
受験資格
受験資格はありません。年齢・性別・学歴に関係なく、誰でも受験できます。
但し、行政書士試験に合格しても、未成年者や成年被後見人・被補佐人、懲戒処分を受けた公務員、禁固刑以上の刑を受けた者などに該当する対象は資格登録が認められません。
試験日時
例年、7月下旬から8月下旬にかけて受験申込みを受け付け、11月の第2日曜日に試験が実施されます。試験時間は、午後1時から午後4時までの3時間です。
試験の方法と内容
行政書士試験は、大きく「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する一般知識等」の2つに分けて択一式及び記述式で実施されます。
問題数と配点は、行政書士の業務に関し必要な法令等(46題)と行政書士の業務に関連する一般知識等(14題)の合計60問、300点満点です。
| 項目 | 行政書士の業務に関し必要な法令等 | 行政書士の業務に関連する一般知識等 |
|---|---|---|
| 試験科目 | 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題 | 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 |
| 問題数 | 46問 | 14問 |
| 試験の方法 | 択一式及び記述式 | 択一式 |
| 配点 | 244点 | 56点 |
試験地
試験地は、全国47都道府県で実施され、現住所や住民票の住所に関係なく、どの試験場でも受験が可能です。
受験手数料(令和4年実績)
10,400円
行政書士試験の難易度
合格基準
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が122点以上(50%以上)
- 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が24点以上(40%以上)
- 試験全体の得点が180点以上(60%以上)
尚、合格基準については問題の難易度を評価し補正的措置が加えられることもあります。
問題の難易度に関わらず、合格基準点が定められているので、合格率は年度によって多少のばらつきが出ます。
合格率
令和4年度は、受験者数47,850人に対して5,802人が合格。合格率は12.13%でした。
平成26年は8%、平成29年は15.7%とばらつきがあります。
難易度
難易度: やや難しい
合格までの学習時間の目安:800時間
行政書士試験のおすすめの通信講座
行政書士試験は、独学でも合格は可能ですが、難易度が高い試験なので通信講座を使って効率よく学習するのが一般的です。
行政書士試験の最もおすすめの通信講座は、何といってもアガルートアカデミーまたはフォーサイトの行政書士試験講座です。
令和3年のアガルートアカデミーの行政書士試験の合格率は全国平均の3.8倍ほど、フォーサイトは全国平均の3.86倍ほどの合格率を誇ります。
行政書士は独立開業におすすめの資格か
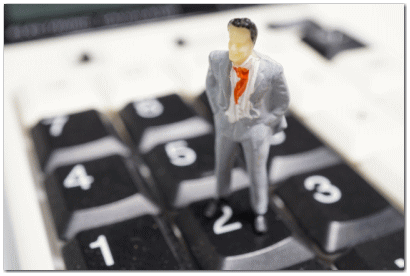
行政書士として独立する際の留意点
行政書士試験は、受験資格がなく他の士業と比較して試験の難易度もさほど高くありません。
にも拘わらず、独占業務が与えられているので独立開業しやすく、また、8士業の一つとあって人気の高い資格です。
会社に勤務しながら学習して資格を取得することができますので会社員にも人気が高く、実際、会社員時代に資格を取得して行政書士として独立開業される方も少なくありません。
定年前に資格を取って定年退職後に独立開業する方もいます。人生経験が豊かで、人脈も広く、また年金収入が見込める定年後・老後の独立にこそ適した資格と言えます。
実際、行政書士試験は、定年後のシニアが一番多くチャンレンジしている資格です。
机と電話・FAX、パソコンなどがあれば自宅を事務所として開業できることから開業資金も少なくてすみ、失敗するリスクも少ないと言えます。
一方で、試験には合格したけど行政書士として登録する人が少ないのもこの資格の特徴です。
その最大の理由が、金銭的な負担が大きいことです。所属する都道府県にもよりますが、登録料には30万円ほどの費用がかかりますし、年会費も10万円ほどかかります。
会社員の時に行政書士試験に合格しても会社員として行政書士の仕事は行えず、これだけの費用がかかる訳ですから、登録しないでおくという選択肢が優先されるのも理解できます。
そのため、将来、独立するかもしれない時のために保険として取得しておく、また、行政書士の資格を転職活動に活かすといった理由で行政書士の資格取得を目指す人も多くいます。
行政書士としての働き方には、専業で活躍する方はもちろん、副業として週末だけ仕事を受注する、知人やホームページを通して依頼を受けた時だけ働く、といった働き方もあります。
行政書士としてバリバリ働き、高収入を目指したいと考えている場合は、他の士業同様、最低限、押さえておかなければならないポイントがいくつかあります。
WEB戦略を構築する
現在は、何か問題があれば、まずはスマホなどを使ってネットで検索します。
近年はホームページやブログなどインターネットを使った集客を積極的に行っている士業事務所が台頭してきている現実もあり、WEB戦略の構築は必要不可欠なものとなっています。
WEBやSNSをライバルよりうまく活用することで、経験や実力では敵わなくても収入面で超えることも可能になります。
特に知り合いとか、近場の行政書士に頼んだのではなく、「債権回収」といったワードでひっかかった行政書士の中からデザインや記載してある内容のしっかりしたホームページの行政書士に依頼しました。以来、15件ほど同じ人に依頼しました。
ネットからのニーズは今後ますます増えてくると思います。
ホームページもただ単に作るのではなく、信頼できそうなデザインにすることや得意分野や料金を明確にするなど、訪問者が安心して依頼できるものにすることが重要です。
WEBを作れば例え昨日開業した人でもベテランを装うことが可能となります。
仕事のネットワークを構築する
独立開業を成功へと導くには人脈作りも非常に重要です。
人脈作りには異業種交流会などに参加して不動産業者や税理士、弁護士などとネットワークを構築するなど、自ら積極的にそういった場に顔を出すことが欠かせません。
また、商工会議所や行政書士会、その他公的機関が定期的に開催する無料相談会など地域のセミナーや行事に参加して、仕事に結びつけるといったことも重要です。
専門分野を掲げる
他の行政書士との差別化を図るためにも、また、依頼者が仕事を頼みやすくするためにも、自分の得意分野・専門分野を決めてアピールするのが有効です。
行政書士の専門分野としては、日本国籍取得、遺言・相続、内容証明郵便・公正証書作成、建設・産廃、運輸・交通、法務・会計、会社法などがあります。
相続問題で困っている時に、「何でもできます」というのと「遺言・相続専門です」という行政書士では、後者に依頼したくなる人が多いのではないでしょうか。
例えば、遺言においては、遺言書の起案・作成の支援、遺産相続においては遺産分割協議書等の作成・相続財産の調査・相続人の確定調査などは行政書士の独占業務ですのでそういった専門分野をアピールすることで他の行政書士との差別化を図ることができます。
現在は、ホームページやブログでもその存在や得意分野をアピールすることができますのでそういったものを活用することも大事な営業の一つとなります。
また複数の分野を掛け合わせることで、他の行政書士が持たない付加価値を作り出すことも可能ですし、司法書士や税理士は難関だとしても、宅建士や社会保険労務士、FPなどの資格を併せ持つことで仕事の幅も広がります。