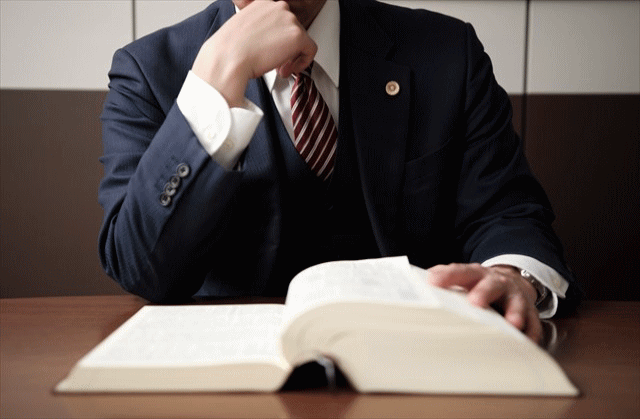ここでは、士業と言われる資格の一覧と各士業の資格試験の難易度をまとめています。
士業とは?
士業とは、資格の名称の最後に「士」が付く国家資格保持者による高度な専門性を持つ職業の俗称です。「しぎょう」「さむらいぎょう」とも呼ばれています。
士業は高度な専門職で責任も大きいため、その業務に従事するには国家資格が必要です。
近年は、相続士や法務士などのように民間資格でも「士」が付けられている資格が増えてきていますが、これらはいわゆる士業ではありません。
また、医師や看護師、美容師など「士」ではなく「師」がつく専門職もありますが、士業とひとまとめにして「士師業」と呼ぶ場合もあります。
国家資格の士業
国家資格の士業は、殆どが比較的難易度の高い国家資格の合格者に与えられる称号で、高度な専門性を持つ職業としてその資格を有する者のみが行うことができる業務が法律で定められている「独占業務」が与えられています。
資格を持っていない方がその業務を行った場合、もしくは有資格者であることを名乗った場合には処罰の対象となります(名称独占)。
業務独占資格なので評価が高く独立しやすいのが特徴です。
民間資格の士業
これに対して、民間資格の士業は、資格の認定や業務の独占性が法的に認められていません。
民間の業者が能力や知識を証明するにとどまります。
以下は、国家資格の士業について解説します。
8士業とは?
士業は、8士業、10士業と呼ばれるものに分類されている資格があります。
8士業とは、士業の中でも、特に、その業務において第三者の戸籍謄本や住民票の写しなどプライバシーに関わる書類を請求できる権限が認められている士業をいいます。
8士業は以下の通りです。
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 土地家屋調査士
- 海事代理士
8士業だからと言って他の士業よりも難易度が高いという訳ではありません。
10士業とは
10士業は、地方公共団体が開催する無料相談会等の相談役になるなどで、企業や個人の問題の相談に乗りアドバイスができる専門性の高い士業のことです。
以下の士業が10士業と呼ばれています。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 司法書士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
8士業のうち、海事代理士を除いた士業に公認会計士や中小企業診断士、不動産鑑定士が加わります。
その他の士業
士業には、8士業、10士業と言われるもの以外にもあります。
このサイトで紹介しているその他の士業(国家資格)には、
- 技術士
- 一級建築士
- マンション管理士
- 宅地建物取引士
- 測量士
- ボイラー技士
- エネルギー管理士
- 電気工事士
- 土木施工管理技士
- 管理栄養士
- 保育士
- 情報処理安全確保支援士
- 全国通訳案内士
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 健康保険福祉士
- 気象予報士
- ファイナンシャル・プランニング技能士
- 建築設備士
- 消防設備士
などがあります。
士業の難易度
士業と呼ばれる国家資格のうち、主要な資格について、受験資格や試験内容、合格率、また、公開されている試験のデータやネット上の口コミなどをもとに難易度を記載しています。
尚、難易度と資格の格付けはほぼ比例しますが、合格率と難易度は比例しません。
これは受験層が異なるためです。
例えば、受験資格が設けられている資格は受験する時点である程度の能力・知識が求められているため、受験資格がない資格と比較すると仮に難易度が同じでも合格率は高めになります。
士業資格の難易度
難易度・偏差値は、あくまでも目安であり、個々人の知識や経験により変わってきますので、参考として捉えて頂けたらと思います。
| 士業資格 | 士業になるためには | 難易度 偏差値 |
合格率と 合格までの 学習期間目安 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 弁護士になるには、通常、司法試験に合格し司法修習を終える必要があります。そして司法試験を受けるには法科大学院を修了するか司法試験予備試験に合格する必要があります。司法試験は国内最難関の試験です。 参考:司法試験の難易度 |
80 | 40%前後
5,000時間 |
| 公認会計士 | 公認会計士になるには、公認会計士試験(短答式と論文式)に合格後、2年間の実務経験と実務補習所での単位取得を経て、最終試験(修了考査)に合格する必要があります。修了考査も合格率50%と甘くはありません。 参考:公認会計士試験の難易度 |
79 | 8~9%
3,500時間 |
| 司法書士 | 司法書士は、不動産の権利に関わる登記手続の専門家です。受験資格はなく、一次の筆記試験と二次の口述試験に合格後、一定の研修を受けると司法書士になれます。合格率は毎年4%前後と狭き門です。 参考:司法書士試験の難易度 |
78 | 5%
3,000時間 |
| 税理士 | 税務のスペシャリストである税理士は、受験資格をクリアした者が税理士試験を受けて合格し、2年の実務経験を経て税理士になることができます。試験は合格率20%未満の5科目全てに合格する必要があります。 参考:税理士試験の難易度 |
77 | 科目合格率 平均10~15% 3,000時間 |
| 弁理士 | 特許の専門家である弁理士は、弁理士試験に合格し、実務修習を修了後、弁理士登録してなることができます。試験は、年齢・性別・学歴・国籍に関係なく誰でも受験できます。合格率は10%弱です。 参考:弁理士試験の難易度 |
76 | 6~9%
3,000時間 |
| 不動産鑑定士 | 受験資格のない短答式試験に合格後、論文式試験に合格し、1~2年の実務修習を修了すれば不動産鑑定士として登録できます。実務修習は、1年コース、2年コースから選択することが可能です。 参考:不動産鑑定士試験の難易度 |
75 | 5%
2,000時間 |
| 技術士 | 技術士は技術分野では最高位の資格と評されています。一次試験に合格後4年~7年の実務経験を積んだ後二次試験に合格することで技術士に登録できます。一次試験の合格率は約50%、二次試験の合格率が15%前後です。 参考:技術士試験の難易度 |
73 | 5%
1,500時間 |
| 中小企業診断士 | 経営コンサルタントと言われる唯一の国家資格。受験資格のない1次試験に合格後2次試験に合格後、実務補習または養成課程を受講することで中小企業診断士になることができます。特定の資格保有者は試験科目の一部免除もあります。合格率は7%程度です。 参考:中小企業診断士試験の難易度 |
70 | 7%
1,200時間 |
| 情報処理安全 確保支援士 |
情報処理安全確保支援士は、情報セキュリティ確保支援を業とする人材確保のために新設された国家資格です。合格率は20%程度です。 参考:情報処理安全確保支援士試験の難易度 |
70 | 5%
1,000時間 |
| 一級建築士 | 令和2年から建築士法の改正により実務経験は、受験資格ではなく免許を受けるための登録要件に緩和されました。合格率は、例年、学科試験が20%前後、設計製図の試験が40%前後となっており、総合合格率が12%前後となっています。 参考:一級建築士試験の難易度 |
67 | 12%
1,200時間 |
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。行政書士に合格している者も受験資格が与えられます。社会保険労務士になるには、試験に合格するほか、実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要です。合格率は5%~7%です。 参考:社会保険労務士試験の難易度 |
65 | 6%
1,000時間 |
| 気象予報士 | 気象予報士は天気予測の専門家です。気象予報士になるには、一般財団法人 気象業務支援センターが実施する気象予報士試験に合格し、気象庁長官に「気象予報士」として登録してもらうことが必要です。気象予報士試験の合格率は5%前後です。 参考:気象予報士試験の難易度 |
65 | 5%
1,000時間 |
| 全国通訳案内士 | 全国通訳案内士は、英語関連の資格では国土交通省の認定を受けた唯一の国家資格で、日本を訪れる外国人観光客を相手に通訳や観光案内を行う通訳のスペシャリストです。 参考:全国通訳案内士試験の難易度 |
65 | 17%
1,000時間 |
| 海事代理士 | 海事代理士は、海事に関する法律の専門家です。近年は、日本の海運会社が安価な外国籍の船舶を使うことが増えたため日本の船籍を持つ船が減り、海事代理士への需要は減ってきています。 参考:海事代理士の難易度や受験資格 |
65 | 50%
900時間 |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士は、不動産の表示に関わる登記手続の専門家です。測量士補の試験に合格後、午前の部を免除されて合格するというケースが殆どです。書式問題には必ず計算問題があります。合格率は例年10%前後です。 参考:土地家屋調査士試験の難易度 |
64 | 10%
800時間 |
| 行政書士 | 行政書士は受験資格のない国家試験に合格することでなることができます。そして約18時間の研修を受けることで特定行政書士となることができます。合格率は10%前後。士業の中では比較的難易度が低い試験です。 参考:行政書士試験の難易度 |
62 | 13%
800時間 |
| マンション 管理士 |
マンション管理士は、管理組合側の立場に立って建物の保全や管理に関する総合的なアドバイスを行います。マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、公益財団法人マンション管理センターにマンション管理士として登録することが必要です。合格率は8%前後です。 参考:マンション管理士試験の難易度 |
62 | 10%
800時間 |
| 管理栄養士 | 管理栄養士は、食事や栄養に関する高度な指導や、栄養素の計算など食事の管理を行う栄養のプロです。病院や福祉施設、小中学校や保育園、保健所、給食センター、スポーツ分野などさまざまな場所で活躍しています。 参考:管理栄養士の難易度 |
62 | 60%
800時間 |
| 通関士 | 通関士は、税関を通す貨物の輸出や輸入に必要な申請書類の作成や手続きを代行したり、申請が許可されなかった場合の不服申し立てなどを行う通関業務のエキスパートです。 参考:通関士試験の難易度 |
59 | 15%
700時間 |
| 測量士 | 建設・土木工事を行う土地についてはかならず測量を行う必要がありますが、測量士は、位置や高さ、長さ、距離、面積などを測量するスペシャリストです。 参考:測量士試験の難易度 |
58 | 15%
600時間 |
| 社会福祉士 | 社会福祉士は、精神保健福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉系の国家資格の一つで、1987年に「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられたソーシャルワーカーの資格です。 参考:社会福祉士試験の詳細 |
58 | 30%
500時間 |
| 保育士 | 保育士とは、乳児から小学校就学(0歳~6歳)までの幼児を、保育所などの児童福祉施設において保育を行う者に与えられる国家資格です。 参考:保育士試験の詳細 |
58 | 20%
500時間 |
| 建築設備士 | 建築設備士は、建築の設備について全般的な知識および技能を持ち、高度で複雑な建築設備の設計や工事監理について建築士に対してアドバイスができることを証明できる資格です。 参考:建築設備士試験の難易度 |
58 | 20%弱
500時間 |
| 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士(宅建士)になるには、宅地建物取引士試験に合格し、一定の要件のもと、都道府県知事の「取引主任者資格登録」を受け、宅地建物取引士証の交付を受けるというステップが必要になります。 参考:宅地建物取引士試験の難易度 |
56 | 17%
350時間 |
まとめ
以上、士業とは何か?士業資格と各士業の資格試験の難易度を一覧形式で解説してきました。
国家資格の中で士業と言われるものは、高度な専門性を持つ職業の俗称で、独占業務があったりするだけあって、その資格試験は他の資格と比較しても試験の難易度が高いのが特徴です。
試験の合格までには、数年単位の時間が必要なものもありますので計画立てて取り組む必要があります。効率よく学習するために先行投資をして通信講座を利用する人が殆どです。
合格後は、高い評価を受け、就職や転職、また独立においても非常に有利になります。
資格で食っていく、手に職をつけたい、人生を逆転させたい、人に評価されたい、高収入を得たい、と思う方は計画を立ててチャレンジしてみて下さい。
士業とそうでない資格の業種別の資格の難易度については、下の記事で紹介しています。
・情報処理技術者試験の種類と難易度
・おすすめのIT・Web関連資格とその難易度
・おすすめの医療事務の資格とその難易度
・おすすめの調剤薬局事務の資格とその難易度
・介護に関する資格とその難易度
下の記事もよく読まれています。