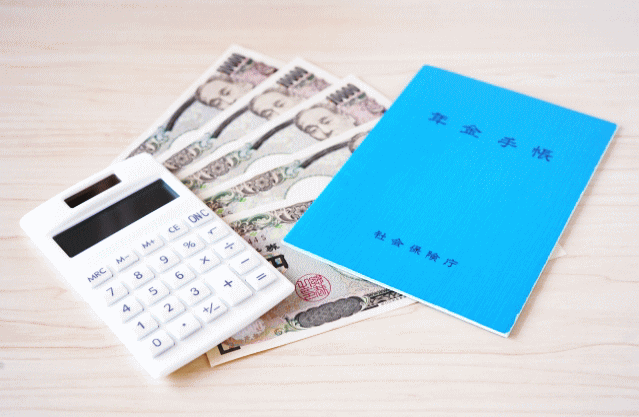ねんきん定期便に書かれた、貰えるであろう年金給付額を見て老後の生活を計画している人もいると思いますが、実際の手取り額はあくまでも税金や社会保険料などが差し引かれた額です。
税金や社会保険料などが引かれた、より正確な年金給付額を把握することで、精度の高い計画を立てることができます。
ここでは、年金から引かれる税金や社会保険料にはどのようなものがあるか、そして、結局のところ、手取りはどれくらいになるか、わかりやすく解説します。
年金にも税金と社会保険料がかかる
公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金がありますが、ここで解説する公的年金は、老後の生活を保障するための年金「老齢年金」のことです。
老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で構成されます。
老齢基礎年金は国民年金、老齢厚生年金は会社員や公務員が加入する厚生年金のことです。
個人事業主・自営業の方の老齢年金は、国民年金部分の老齢基礎年金のみとなります。
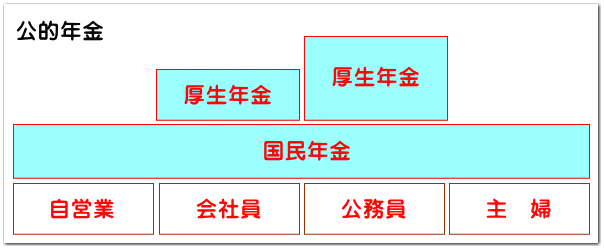
そして、公的年金(老齢年金)は所得として扱われ、税金や社会保険料の対象となります。
従って、実際の手取り額は、これらを差し引いた額となります。
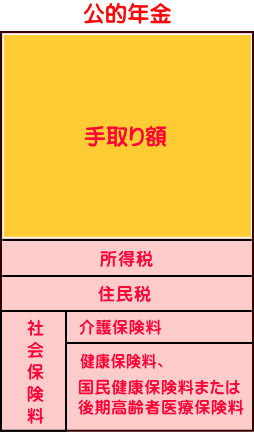
公的年金から差し引かれる税金や社会保険料を一つづつ見ていきます。
年金から引かれる税金
まずは、年金から差し引かれる税金からです。
所得には、以下の通りその性質から10種類の所得があり、公的年金は、このうちの雑所得に該当し、所得税と住民税の課税対象となります。
| 所得の種類 | 所得の内容 |
|---|---|
| 利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得 |
| 配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
| 不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得 |
| 事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得 |
| 給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
| 退職所得 | 退職によって受ける所得 |
| 山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得 |
| 譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得 |
| 一時所得 | クイズの賞金や満期保険金などの所得 |
| 雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得 |
公的年金の所得税の計算の仕方
公的年金は雑所得となり、所得税と住民税の課税対象となりますが、これらの税金は貰う公的年金全額にかかってくる訳ではありません。
まずは、公的年金の所得税の計算の仕方についてみてみます。
所得税とは1年間の所得にかかってくる税金です。
公的年金の所得税の課税の対象となる課税所得は、公的年金から、決められた控除額を差し引いて雑所得を求め、さらに雑所得から所得控除を差し引いて求めます。
公的年金の課税所得 = 公的年金に係る雑所得の金額 - 所得控除
公的年金に係る雑所得の金額の計算
公的年金に係る雑所得の金額は、令和3年度から見直されました。
65歳未満と65歳以上で異なり、以下のテーブルの計算式による控除額を差し引いて算出します。
公的年金等控除額(合計所得金額1000万円以下の場合)
| 年金受取時の年齢 | 年金収入額 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円未満 | 600,000円 | |
| 130万円以上410万円未満 | 年金収入額の25% + 275,000円 | ||
| 410万円以上770万円未満 | 年金収入額の15% + 685,000円 | ||
| 770万円以上1,000万円未満 | 年金収入額の5% + 1,455,000円 | ||
| 1,000万円以上 | 195.5万円 | ||
| 65歳以上 | 330万円未満 | 1,100,000円 | |
| 330万円以上410万円未満 | 年金収入額の25% + 275,000円 | ||
| 410万円以上770万円未満 | 年金収入額の15% + 685,000円 | ||
| 770万円以上1,000万円未満 | 年金収入額の5% + 1,455,000円 | ||
| 1,000万円以上 | 年金収入額の5% + 1,455,000円 | ||
例えば、65歳で公的年金を年間200万円受け取る場合は、
公的年金に係る雑所得の金額は、200万円 – 110万円で、90万円になります。
同じく、65歳で公的年金を年間400万円受け取る場合は、
公的年金に係る雑所得の金額は、400万円 -(400万円 × 0.25 + 275,000円)で、272万5,000円になります。
公的年金の課税所得の計算
公的年金に係る雑所得の金額が算出されたら次に所得控除を引いて課税所得を算出します。
所得控除とは
所得控除とは、
- 基礎控除
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- 障害者控除
- 医療費控除
などです。
このうちの基礎控除は所得金額が2,500万円以下の場合は、一律48万円となります。
例えば、65歳で公的年金を年間200万円支給される場合に、社会保険料控除(国民健康保険税+介護保険料)が15万円ある場合、
課税所得は、先ほどの計算で公的年金に係る雑所得金額は90万円でしたので、それから基礎控除の48万円と社会保険料控除の15万円を差し引いて27万円となります。
公的年金の課税所得 = 90万円 – 48万円 – 15万円で、27万円
つまり、公的年金の所得税は、この27万円にかかることになります。
従って、所得税は、
- 65歳未満の方は公的年金の受給額が60万円以下
- 65歳以上の方は公的年金の受給額が110万円以下
であれば非課税となり、所得金額が2,400万円以下の場合は48万円の基礎控除が一律適用されますので、結果として、
- 65歳未満の方は公的年金の受給額が108万円以下
- 65歳以上の方は公的年金の受給額が158万円以下
の場合は、所得税を支払う必要はないということになります。
公的年金の所得税の計算
公的年金の課税所得を算出したら最後に所得税率を掛けて所得税額を算出します。
上記の例でいうと、公的年金の課税所得は27万円でしたので、その場合は税率は5.105%(税率5%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算)なので所得税額は1万3,784円となります。
※税率は、本来、所得に応じた税率5%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した額ですが、下のテーブルでは、復興特別所得税(所得税額の2.1%)は加味していません。
| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、課税所得額が200万円ある場合は、200万円 × 10%(税率)- 97,500円(控除額)で、所得税は102,500円となります。
公的年金の住民税の計算の仕方
次に、住民税です。
住民税はその地域の住人が負担する税金で、
- 都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と
- 市区町村が課税する区市町村民税
を合わせたものです。
住民税の計算の仕方
住民税も公的年金の課税所得にかかってきます。
住民税には前年の所得にかかる所得割と均等にかかる均等割があります。
住民税の所得割の計算
住民税の所得割の部分は、所得税と同じように、まずは、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いて、課税所得を求めて算出します。
住民税の基礎控除は43万円(2021年分から)で、住民税の税率は所得の金額にかかわらず10%(区市町村民税:6%と道府県民税・都民税:4%)です。
従って、例えば、65歳で公的年金の支給額が200万円の場合、社会保険料控除(国民健康保険税+介護保険料)が15万円ある場合、
住民税の課税所得は、公的年金に係る雑所得の金額を求めた後、基礎控除の43万円と社会保険料控除の15万円を差し引いて求めます。
例えば、公的年金が200万円の場合は、雑所得が90万円でしたので、住民税の課税所得は、基礎控除の43万円と社会保険料控除の15万円を差し引いて32万円となり、住民税の所得割の部分の税金は、10%の3.2万円になります。
公的年金の住民税の均等割
均等割りは一律5,000円~6,000円程度(市区町村によって異なります)です。
公的年金の住民税額
従って、住民税の額は、公的年金が200万円で社会保険料控除が15万円の場合、所得割の3万2,000円(32万円 × 10%)と、均等割の5,500円ほどを足して37,500円ほどとなります。
年金から引かれる社会保険料
公的年金には、所得税と住民税のほか、社会保険料がかかります。
年金から差し引かれる社会保険料には、国民健康保険料(75歳以上なら後期高齢者医療保険料)と介護保険料があります。
介護保険料は、40歳以上の方にかかる保険料です。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は国民健康保険料の中に介護納付金分が含まれているため別々に支払うことはありませんが65歳以上の方は別々に支払うことになります。
公的年金の社会保険料の計算の仕方
国民健康保険料
65歳以上の国民健康保険料は、基礎賦課額(医療分)と後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)を合わせたものです。40歳から64歳の加入者はこれに介護分保険料がプラスされます。
国民健康保険料は、自治体によっては国民健康保険税とも呼ばれ、世帯単位で所得割、均等割、平等割の金額を計算して、それらを合計したものになります。
- 所得割:世帯の所得に応じて課される金額
- 均等割:世帯の人数に応じて課される金額
- 平等割:1世帯ごとに課される金額
国民健康保険料の算定に用いる課税所得は、公的年金から、所得税の算出の欄でも解説した控除額を差し引き、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額43万円を控除した金額です。
所得税や住民税と異なり、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除はありません。
例えば、65歳で公的年金を200万円受け取る場合、公的年金の国民健康保険税の算定に用いる課税所得は、200万円 – 110万円 – 43万円で、47万円になります。
そして、この47万円をもとに所得割を算出し、均等割、世帯割の金額を合計して算出します。
この算出の仕方は住んでいる地域によって異なり、その計算式も複雑です。
例えば、私が住んでいる長崎では、以下の通りです。
| 医療分 | 後期高齢者 支援分 |
介護分 (40歳~64歳まで) |
説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 8.6% | 3.1% | 2.6% | 加入者の前年中の所得に応じて加算される額。所得から基礎控除額43万円を引いて、左記の所得割率を掛けます。令和3年度は令和2年の1月から12月の所得を使います |
| 均等割 | 24,200円 | 8,500円 | 9,800円 | 加入者一人につき加算される額です |
| 世帯割 | 23,800円 (注1) |
8,300円 (注1) |
6,500円 | 一世帯ごとにかかる基本額です |
| 課税限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 | 最高額は99万円です。一世帯につきこれ以上は課税されません |
(注1)世帯内の国民健康保険加入者が(75歳になるなどして)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したために、被保険者の人数が1人になった世帯は、医療分と後期高齢者支援分の世帯割が5年が経過する年の年度末まで半額になります。
この場合、65歳時の国民健康保険料は、
- 所得割医療分:4万420円(47万円×8.6%)
- 所得割後期高齢者支援分:1万4,570円(47万円×3.1%)
- 均等割医療分:24,200円
- 均等割後期高齢者支援分:8,500円
- 世帯割医療分:23,800円
- 世帯割後期高齢者支援分:8,300円
の合計:119,790円となります。
尚、前年中の所得が一定の基準以下の世帯は均等割額と世帯割額を減額する制度があります。
それぞれの市区町村の国民健康保険料の算出の仕方や、均等割額と世帯割額を減額する制度は、自治体のホームページで確認することができます。
介護保険料
65歳以上の人の介護保険料は、基本的に、65歳以上の介護サービスにかかる費用の総額を65歳以上の方の人数で割って算出した「基準額」をもとに、その人の所得に応じた段階ごとに異なる割合をかけて算出する、といった計算で算出されます。
住んでいる市町村で「基準額」も「所得に応じた段階」も異なりますので、当然、市町村で介護保険料も異なります。
算出の仕方は、自治体のホームページで確認することができます。
後期高齢者医療制度の保険料
75歳になって国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ると、国民健康保険料は支払わなくてよくなるかわりに後期高齢者医療制度の保険料を支払うことになります。
保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する 「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。
住んでいる市町村で保険料が異なります。
結局、年金の手取りはどれくらいか?
以上のように、公的年金は、所得税・住民税・社会保険料の対象となり、原則として年金から天引されて支給されます。
負担額としては所得税や住民税より社会保険料の方が重くなります。
そして、年金の手取り額は、総支給額の8.5割~9割というのが一つの目安です。
例えば、今回例としてあげた65歳で公的年金が200万円支給される場合は、所得税が1万4,000円ほど、住民税が37,500円ほど、社会保険料が12万円ほどとなり、手取りは、183万円ほどとなります。
これはあくまでも目安で、特に社会保険料は収入額や家族構成によって変わってきます。
まとめ
以上、年金から引かれる税金や社会保険料にはどのようなものがあるか、そして、結局のところ、手取りはどれくらいになるか、解説してきました。
公的年金(老齢年金)からは所得税・住民税・社会保険料が点引きされて通帳に振り込まれますが、その額は支給額のおよそ1割から1.5割ほど。つまり8.5割から9割程度が手取りで受け取れる額となります。
この割合は、収入によって異なり、収入が少ないほど手取りの額の割合は高くなります。
しかし、今後は少子高齢化が進む中、ある程度の社会保障を維持していかなければならず、必然的にその負担額は大きくなってくることが予想されます。現在、60歳未満のシニア層の方は将来は2割ほど差し引かれると考えておいた方がいいかもしれません。